朝のリビングで、突然こぼれた涙
朝の慌ただしい時間。
リビングでランドセルを背負い、
玄関に向かったうちの長女(10歳)が、
突然ぽろぽろと涙をこぼし始めました。
「どうしたの?」と声をかけても、
すぐには答えてくれませんでした。
だけど、少し待って、
静かに問いかけると、
震える声でこう言ったのです。
「登校班で行きたくない……」

初めて聞いた「行きたくない」という言葉
正直、少し驚きました。
長女はこれまで、
どんなにしんどそうでも、
我慢して登校してきたから。
「行きたくない」なんて言葉、今まで一度も聞いたことがなかったんです。
さらに聞いていくと、
長女はこんなふうに話してくれました。
「班の中にすごくにぎやかな子がいて、
ずっとその子のそばで歩くのがつらい。
30分以上、逃げ場がない感じがするの……」
このとき私は、
長女がどれだけの時間をかけて、
どれだけの勇気を出して、
その気持ちを言葉にしたのかを思って、
胸がぎゅっとなりました。

5年間、我慢し続けていた長女
長女は現在、小学5年生です。
でも、
自分のしんどさを言葉にするのは、これが初めてのことでした。
これまで、
気になることや不安なことがあっても、
長女は「がんばるね」と笑っていたし、
泣くことはあっても理由はなかなか話せませんでした。
それがこの日、
「いやだ」「行きたくない」と、はっきり言ってくれた。
その一言が、
私にはとても尊く、
大きな成長に感じられました。
きっと、
言う前に何度も迷ったと思います。
「言っても伝わらないかも」とか、
「相手に悪気はないのに」って、
自分を責める気持ちもあったかもしれない。

母の返答「一緒に学校に行こう」
でも、
長女は言ってくれた。
だから私は、
咄嗟にこう返しました。
「うん、それでいい。今日は一緒に学校に行こう。保健室で過ごしても大丈夫だからね」

登校班での具体的な困りごと
私自身、
長女の話を聞いて初めて気づいたことがありました。
それは、
「登校班」という一見当たり前に見える仕組みの中に、
こんなにもつらさがあったということです。
長女がしんどいと感じていたのは、
・大きな声や笑い声がずっと近くにあること
・並んで歩く距離感の近さ
・30分間、立ち止まれない、逃げられないということ
本人はその感覚の理由を説明しづらかったかもしれません。
でも、
感覚的な”しんどさ”って、そういうものなんですよね。
目に見えないからこそ、理解されにくい。

毎日続いていた、からかいの言葉
さらに後から聞いた話では、
にぎやかな子が列を乱したあと、
戻ってきて長女の隣に来たときに、
「おばさんみたい!」「おばけ!」とからかいのような言葉をかけてくることもあったそうです。
それが毎日のように続けば、
「行きたくない」と思って当然ですよね。

手をつないで、学校へ
その日は、
私が学校まで一緒に歩いて行きました。
長女はずっと私の手を離さず、
学校に着いてからも「保健室に行きたい」と言いました。

保健室で見えた、登校班の構造
保健室の先生がゆっくり話を聞いてくださって、
そこで初めてわかったことがありました。
そのにぎやかな子(Aちゃん)は、
列の後ろに行きたがることが多くて、
班長さんに注意されては前に戻される。
でも、”しぶしぶ戻る”そのポジションが、
長女の隣だったのです。

「仕組みの側を見直す」という視点
保健室の先生はこう言ってくださいました。
「それなら、最初から後ろにしてあげたらいいかもね。
ウロウロしなくなるかもしれない」と。
私はその言葉に、
すごく救われた気がしました。
子どもを責めるでもなく、
長女に「がまんしてね」と言うでもなく、
“仕組みの側を見直す”という視点。
「本人に問題がある」のではなく、
環境を整えること。
それができれば、
長女はもっと安心して登校できるんじゃないかと思えたのです。

「いやだ」が言えた日は、自分を守った日
この経験を通して、
私は強く思いました。
「いやだ」が言えたあの日は、長女が自分自身を守った日だったんだと。
無理にがんばらなくていい。
「我慢しなきゃ」と思わなくていい。
まずは自分の気持ちを知って、それを伝えてみること。
それは、子どもが少しずつ世界と関わっていくための大切な一歩なんだと感じました。
そして親としての私は、
その一歩をどうか見逃さずに、
「うん、言えてえらかったね」と受け止めていける存在でありたいと思います。
子どもが少しずつ、
自分のペースで世界を広げていけるように。
その歩みに、そっと並んで歩いていけたらと思っています。
読んでくださり、ありがとうございました。

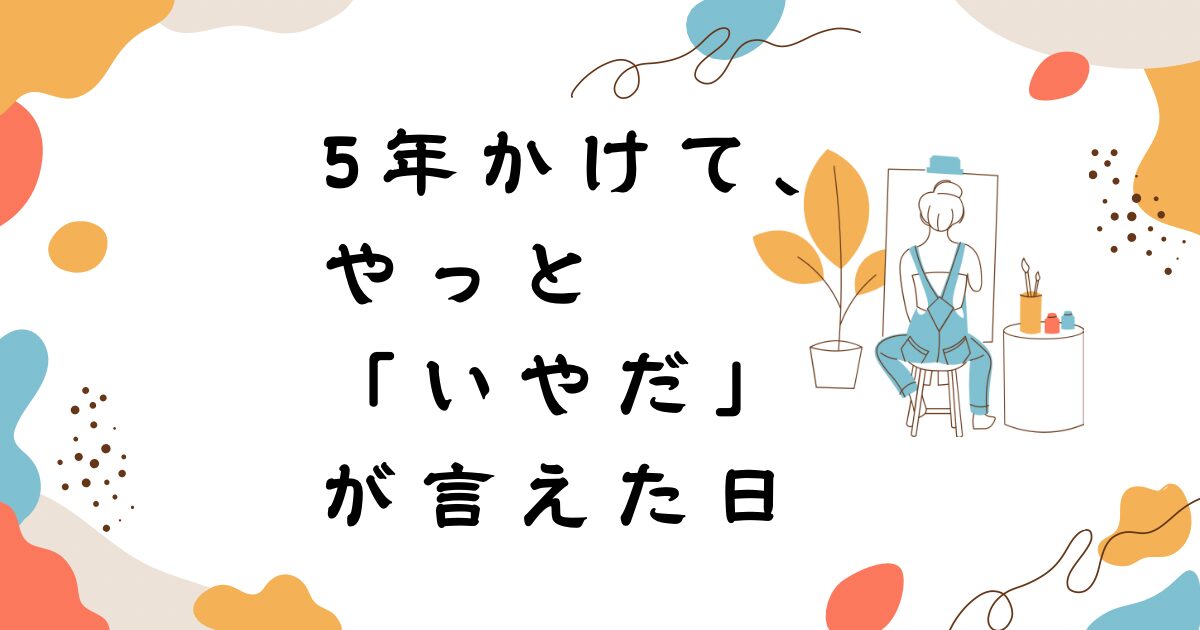
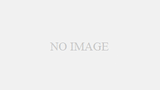
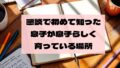
コメント