
こんにちは、こまちです!
あなたは、家族との毎日の食事で、こんな悩みはありませんか?
☑子どもの食べるもの、食べないものがハッキリしている
☑「一口だけでも食べてみようか」が通じず強制すると癇癪を起こす
☑食べてくれないので同じメニューのローテーションになっている
☑食事の時間が自分にも子どもにもストレス
「好き嫌いしないの!」
「わがまま言わないで食べなさい!」
ついつい言ってしまいそうですが、
実はそれ、
発達障害児ならではの「感覚過敏」かも知れません。

我が家の長男は2歳の頃、
注意欠如多動症(ADHD)、
自閉スペクトラム症(ASD)、
軽度知的障害と診断されました。
食事にムラが出始めたのは1歳半頃。
保育園のお便り帳に「給食の○○が食べれませんでした」という文面が毎日書かれるように。
食事について責められている気分になり、お便り帳を見るのが億劫でした。
この偏食には悩まされる時期が続き、実は、今なお続いています。
しかしある時、
「感覚過敏」について知る機会がありました。
調べてみて分かったのは、
自閉スペクトラム症の人々は食べ物に対して過敏に反応する傾向があるということです。
・特定の食品にしか興味を示さない
・食品の色、形状に敏感
・食品の味覚過敏
・食品のブランドにこだわる
完全に、長男と一致…!
つまり、長男の極端な偏食はわがままじゃなくて、感覚過敏っていう体質なんだ!
納得したと同時に、目の前がパッと明るくなりました。
心の中には、
「しつけがなってないからわがまま言って食べないんだ…」
と思う気持ちが少なからずありましたから。
ということで、この記事では、5つの感覚過敏の観点から発達障害児の「偏食」について解説していきます。
「今日もまた食べてくれないんじゃないか」と食事の時間が怖くてたまらない方、
「いらない」と食事をお皿ごと投げられてイライラしてしまう方、
めちゃくちゃ分かります…!!
悩みますよね…。
だからこそ正しい知識を味方につけて、
悲しい食事時間とサヨナラしましょう!

偏食=好き嫌いではない
発達障害の子どもたちには、「偏食」のあるケースが多いです。
偏食は単なる「好き嫌い」とは違い、
子どもによって傾向や原因があると言われています。
例えば、
☑決まった色
☑決まった形
☑決まった温度
☑決まった席
へのこだわりが強く、見たことのない食べ物への拒否が起こります。
これらは過敏性ゆえの行動で、
「好き嫌い」とは性質の異なるものです。
感覚過敏とは
感覚過敏には5つの要素があります。
- 視覚
- 味覚
- 聴覚
- 触覚
- 経験
これらの要素を「食事」にフォーカスすると…
- 視覚…色や形へのこだわり
- 味覚…決まった味、温度へのこだわり
- 聴覚…周囲の音(騒がしい、静か)へのこだわり
- 触覚…食材の感じ方がみんなと違う
- 経験…未知のものは警戒する
このようになります。
うちの息子は、
チョコチップパン、麺、お肉、甘い玉子焼きしか食べない時期が長く続きました。
特に「未知のものは警戒する」がとても強くて、
お皿を床に置く、イスに座らない、ベビーベッドへ逃げ込むなどの行動が食事のたびにありました。
「ひと口だけがんばろうね」
「ごはんの列車がいくよ~」
と促しても癇癪を起こします。
一品でもいいから興味を持つように色々な食事を出してみても無関心。
食べられるものに具材を混ぜても目ざとく見付けてより分けます。
そんな長男との攻防に疲れてしまったわたしは、文句を言わずに食べてくれるものを渡してしまう始末……。
そんな食事時間はストレスでしかなく、辛いものでした。
でも、「感覚過敏」を知ってから、アプローチ方法を工夫することが出来ました!
感覚過敏への対応
4歳の食事について、まず最初に把握した4項目がこちらです。
- 食べるものは何?
- ①の食べ物に共通することは?
- 食べないものは?
- ③の食べ物に共通することは?
これを書きだしていきます。
1.食べるものは何?
→唐揚げ、ナゲット、ポテトチップス、スナック菓子が大好き。
2.①の食べ物に共通することは?
→「揚げる調理法」が大好き。
3.食べないものは何?
→生野菜、刺身など生ものは食べない。タレ、ドレッシングがかかっていると食べない。
4.③の食べ物に共通することは?
→ねっとりしたもの、ヌルっとした見た目が苦手。
この4項目を埋めれたら、
次に食べられないものを食べられるものの調理法にします!
①にもあるように、肉食系男子の長男は、3食プラスおやつでも食べられるくらい唐揚げが大好きです。
なので、大嫌いな魚をフライにして渡しました。
これがまさかのヒット!
ポテトチップスのように手に取ってポリポリ食べました!!
もちろん、ドレッシングは無しです。
見た目が違うだけで…食べる!!
そこからいろいろな「見た目の変化」を試しました。
ヒットした「揚げる」を駆使して
野菜を天ぷらにしたり、
ぜったいに食べない白米は
ふりかけを使ってみたり、
ひと口大のおにぎりにしてみたり、
まったく口にしなくなったフルーツは
ジューサーでジュースにしてみたり……。
これだけ試しても、食べないものは食べません。
でも、長男は感覚過敏のどれに当てはまるのかを知り、対応を考えることで、
食事への工夫の仕方への糸口が見えてくるかと思います。
これは、どのような参考書や資料、
データをあさっても、
まさに今のうちの子!とピタリと当てはまるケースはないため、
地道に探っていくしかないんですよね。

我が家での工夫
毎日の食事が修行になってしまっていた我が家。
楽しい食卓を取り戻すために決まりを考えました。
☑食べることを無理強いはしない。でも、目を慣れさせるために食卓に出す
☑例え口に入れなくても、手に取っただけで「〇〇に興味を持った!」と喜ぶ
☑家族が食べるところを見せる
☑気分が乗らないときには一人の場所で食べてもいいルールにする
☑食べられる品目が少なくても、「食べられるものだってある!」と考える
☑感覚過敏の観点から工夫を考え、ヒットしなければ「今はまだその時じゃない」と思う
☑成長曲線内にいるのなら、「低栄養状態ではないので大丈夫」と考える
いかがですか?
ずいぶんと緩い食卓になりました(笑)

まとめ
もうね、分かりました。
「感覚過敏」という特性がある以上、
避けては通れないのが「偏食」です。
これは、親のしつけとは関係がありません。
わたしのためにもう一度言います。
偏食は、親のしつけとは、関係なしです!
でも、食べないことを「あきらめる」わけじゃありません。
食べない行動を「受け入れる」のが大切です。
食べられるものが極端に少ないとしても、
いま、食べられるものを大切にしましょう。
そして、料理方法の組み合わせで工夫できることはないかな、と新しい道を見付けていきましょう。
わたしも今まで手を変え品を変えやってきましたが、
食べない、投げる、癇癪を起こすなど、
わたしも長男も食事の時間がストレスになっていました。
特に、3食用意する休日なんて、もう絶望。
でも、「感覚過敏」を知ってから、
「あー、この子はこういう体質なんだ~」と
ストレスを軽くすることができました。
また、2歳のときより3歳、
3歳のときより4歳と、
食べられるものがひとつ、ふたつと増えてきました。
4歳にとって食べ物が「未知のもの」から「あーこれ何か知ってるー」の認識になったからかも知れません。
偏食をなくす特効薬や魔法はありません。
けれど、ゆっくり少しずつ、
美味しく食べられるものが増えていくように工夫することで、偏食は軽減できるものです。
おいしく食べる姿が見たい…!
そう思ったあなた。
まず、うちの子は何が好き?調理方法は?と、考えることから始めましょう。
そして、楽しいごはんの時間を楽しみましょう。

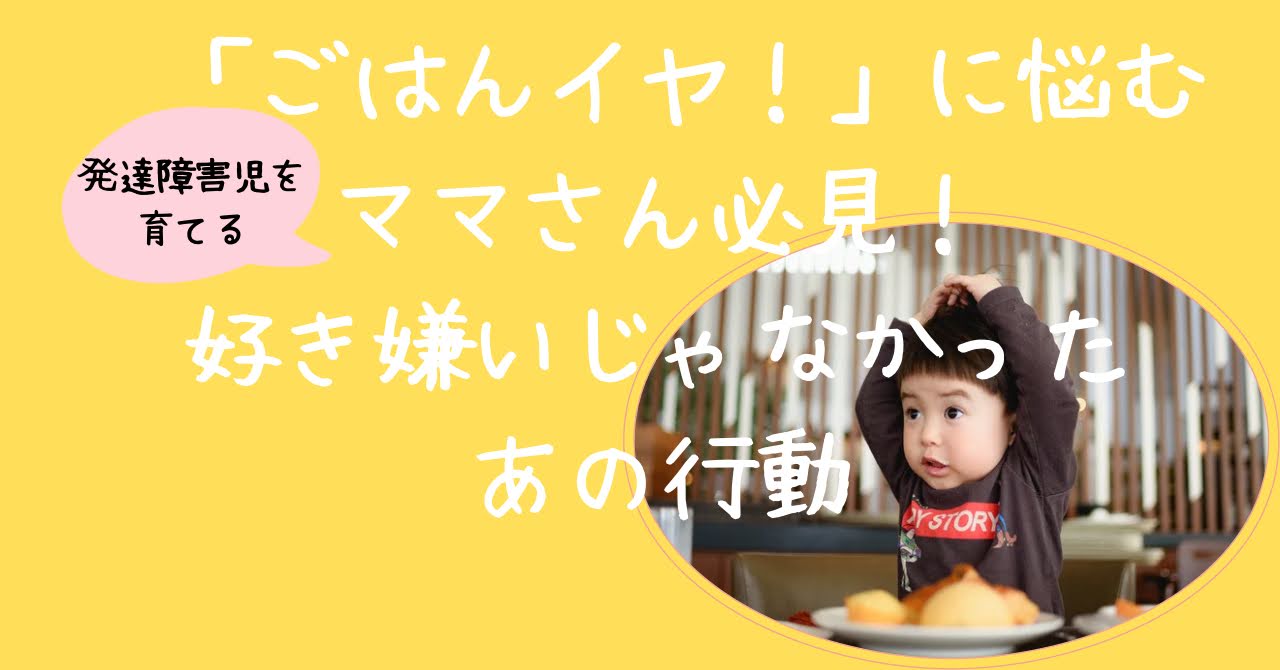
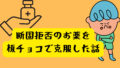
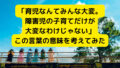
コメント